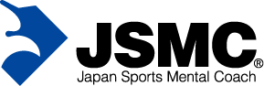はじめに
指導の現場に長くいると、
ふと立ち止まって考えることがあります。
「自分は、いま怒っているのか。
それとも、叱っているのか。」
似ているようで、この二つはまったく違う。
けれど現場では、しばしば混同されています。
声を荒げれば「叱った」ことになり、
強い言葉を使えば「指導した」ことになる。
そんな空気が、どこか当たり前のように残っています。
でも本当にそうだろうか、と感じる瞬間が増えてきました。
怒鳴られた選手が、萎縮して動けなくなる姿。
正論をぶつけられて、自信を失っていく子ども。
「正しいことを言ったはずなのに、なぜか伝わらない」
そんな指導者側の戸惑い。
その光景を見るたびに、
私はこう思うのです。
もしかしたら私たちは、
「何を言うか」ばかり考えて、
「どう伝わるか」を置き去りにしてきたのではないか、と。
そもそも怒るとは何なのか。
叱るとは何なのか。
そして、本当に目指すべき指導の形とは何なのか。
スポーツの現場で、
コーチとして多くの選手と向き合ってきた中で、
少しずつ見えてきたことがあります。
それは、
怒ることでも、叱ることでもなく、
伝わることこそが、指導の本質なのではないか
という感覚でした。
このコラムでは、
怒ると叱るの違いを整理しながら、
「伝わる指導」とは何かを、あらためて考えてみたいと思います。
まずは、
私たちが無意識にやってしまいがちな
「怒る」という行為から見ていきます。
第1章|怒るとは「感情の放出」である
まず最初に、少し冷静に考えてみたいことがあります。
「怒る」という行為は、
本当に指導と言えるのだろうか、という問いです。
現場ではよく、
「怒るのも愛情だ」
「本気だから怒るんだ」
そんな言葉を耳にします。
確かに、
その気持ちは分かります。
真剣だからこそ、感情が動く。
期待しているからこそ、腹が立つ。
ただ、感情が動くことと、
それが「教育として機能すること」は、
実はまったく別の話です。
ここで少しだけ、科学的な視点を挟んでみます。
人が怒りを感じているとき、
脳では「扁桃体」という部分が強く活動します。
扁桃体は、恐怖や怒りなど、
生存に関わる原始的な感情を司る場所です。
いわば「反射の脳」。
一方で、
理性的な判断や、言葉の選択、
「どう伝えるか」を考えているのは
前頭前野という部分です。
いわば「考える脳」。
怒りが強くなると、
この前頭前野の働きは一時的に低下します。
つまり、
考えて話しているつもりでも、
実際には
「反応しているだけ」
になってしまうのです。
これを心理学では
情動ハイジャックと呼びます。
感情が理性を乗っ取ってしまう状態。
だから怒っているときほど、
言葉は雑になり、
伝え方は荒くなり、
後から「言い過ぎた」と後悔する。
これは性格の問題ではなく、
脳の構造上、誰にでも起こる自然な反応です。
ここが、とても大事なポイントです。
怒るという行為は、
相手のための行動というより、
自分の感情を処理するための反応に近い。
「なんでできないんだ」
「何回言わせるんだ」
こうした言葉の主語は、たいてい「自分」です。
自分が困った。
自分が期待を裏切られた。
自分がイライラした。
だから怒る。
それは指導というより、
感情の放出に近い。
さらに言えば、
怒られた側の脳にも変化が起きます。
強い口調や威圧的な態度を受けると、
相手の脳もまた扁桃体が優位になります。
するとどうなるか。
身体は「危険だ」と判断し、
防衛モードに入る。
呼吸は浅くなり、
筋肉は硬くなり、
視野は狭くなる。
これはスポーツにおいて、
最もパフォーマンスが落ちる状態です。
集中力も、判断力も、創造性も下がる。
つまり怒ることで、
「良くなってほしい」と思っているはずの相手を、
無意識に“動けない状態”に追い込んでしまうのです。
ここまで整理すると、
だんだん見えてきます。
怒るとは、
相手を育てる行為というより、
自分の感情に飲み込まれている状態なのかもしれない、と。
少なくとも、
冷静に相手の成長を考えられている状態ではない。
だから私は、
怒ることを「指導」だとは思っていません。
まずはここを、
静かに手放してもいいのではないか。
そう感じています。
では次に、
怒るとは違う「叱る」という行為について、
もう少し丁寧に考えてみたいと思います。
第2章|叱るとは「意図的なフィードバック」である
── 禅に学ぶ、静かな指導
怒ることが、
感情に飲み込まれた反応だとするなら。
では「叱る」とは、何なのだろう。
多くの人が、
叱る=強く言うこと
叱る=厳しく注意すること
そんなイメージを持っています。
けれど本来、叱るとは
声の大きさの問題ではありません。
叱るとは、
意図を持って、相手の行動を正すためのフィードバックです。
そこには怒りは必要ありません。
むしろ、怒りが混ざった瞬間に、
叱るは怒るへと変質してしまいます。
だから叱るために必要なのは、
熱量ではなく、静けさです。
ここで、私はよく禅の言葉を思い出します。
「平常心是道(びょうじょうしんこれどう)」
平常心こそが道である、という意味です。
特別な状態ではなく、
感情に振り回されない、いつもの心。
禅では、
心が波立っているときは、物事の本質は見えないと考えます。
怒りや焦りに飲み込まれているとき、
私たちは相手を見ているようで、
実は自分の感情しか見ていない。
叱るとは、
この「波」を静めたあとに、初めてできる行為なのだと思います。
感情をぶつけるのではなく、
事実だけを見る。
人格ではなく、行動を見る。
評価ではなく、可能性を見る。
そのうえで、
「今のプレーだと、次も同じミスが起きるよ」
「ここを変えれば、もっと良くなる」
そう伝える。
静かで、具体的で、相手の未来に向いた言葉。
それが本来の叱るだと、私は考えています。
禅に、こんな教えもあります。
「和顔愛語(わげんあいご)」
やわらかな表情で、愛のある言葉を使いなさい、という意味です。
厳しいことを言ってはいけない、という話ではありません。
同じ内容でも、
表情や語気ひとつで、
相手の受け取り方はまったく変わる。
だからこそ、
伝え方そのものが修行だという教えです。
叱るとは、
相手をコントロールする行為ではなく、
自分を整える行為なのかもしれません。
自分の心を整え、
言葉を選び、
本当に相手のためになる一言を探す。
実は、怒鳴るより、はるかに難しい。
エネルギーもいる。
だから多くの人が、
無意識に怒る方へ流れてしまう。
怒るは反射。
叱るは選択。
この違いは、とても大きいと思っています。
ただ、ここでさらに考えたくなるのです。
言葉が通じる大人やアスリートに対して、
そもそも「叱る」という形は本当に最適なのだろうか、と。
叱るという行為もまた、
どこか「上から下」への構図を含んでいる。
もっと別の関わり方があるのではないか。
そう感じるようになりました。
その先に見えてきたのが、
叱ることよりも、
伝わることを大切にする指導でした。
次章では、
怒るでも、叱るでもない、
もう一段深い「関わり方」について考えてみたいと思います。
第3章|本当に大切なのは「伝わること」だった
── 叱るを超えて、相手に合わせるという在り方
怒るのではなく、叱る。
感情ではなく、意図を持つ。
ここまで整理すると、
指導としては十分成熟しているようにも思えます。
けれど、現場に立ち続けていると、
もう一つの壁にぶつかります。
それは、
「正しく叱ったはずなのに、なぜか伝わらない」
という現実です。
冷静に、理論的に、
相手のためを思って言葉を選んだ。
それなのに、
「怒られた気がする」
「否定された気がする」
「怖い」
そう受け取られてしまうことがある。
逆に、
励ますつもりで言った一言がプレッシャーになったり、
檄を飛ばしたつもりが威圧に感じられたりもする。
ここで、私は気づかされました。
指導とは、
「何を言ったか」では決まらない。
「相手がどう受け取ったか」で、すべてが決まる。
これは少し残酷な事実です。
どれだけ正しいことを言っても、
どれだけ善意があっても、
伝わらなければ意味がない。
コミュニケーションの結果は、
常に「受信側」が決める。
つまり、
叱ったかどうかではなく、
叱られたと感じたかどうか。
励ましたかどうかではなく、
励まされたと感じたかどうか。
そこがすべてなのです。
そう考えたとき、
私はふと思いました。
もしかしたら、
「叱る」という行為そのものが、
もう一段階手前の技術なのかもしれない、と。
叱るは、確かに怒るより成熟しています。
でも、まだ「伝える側の論理」に立っている。
「正しいことを言っている」
「相手のために言っている」
この時点で、まだ主語は自分です。
けれど本当に必要なのは、
そこからもう一歩進んで、
相手の世界から考えることなのではないか。
同じ言葉でも、
ある選手には背中を押す一言になり、
ある選手には心を閉ざす一言になる。
ある人には「叱責」に聞こえ、
ある人には「信頼」に聞こえる。
人はそれぞれ、
性格も、経験も、傷つきやすさも、
受け取り方も違います。
だから指導とは、
正解の言葉を探す作業ではなく、
この人には、どう届くだろうか
この人には、どんな言い方なら伝わるだろうか
と、想像し続ける営みなのだと思います。
禅の言葉に
「随処作主(ずいしょさしゅ)」
というものがあります。
どんな場所でも、主体的に振る舞え、という意味ですが、
私はこれを
「状況に合わせて自在に在れ」
という教えとして受け取っています。
型に固執しない。
やり方に執着しない。
目の前の相手に合わせて、柔らかく変化する。
水のように形を変える在り方。
怒らない。
叱らない。
それでも、自然と伝わる。
そんな関係性が築けたとき、
指導は初めて「技術」ではなく「在り方」になるのだと思います。
怒るでもなく、
叱るでもなく、
ただ、届く。
そこを目指すことこそ、
我々が考える指導のゴールです。
そしてそれは、
トレーナーというより、
コーチという在り方に、
より近いのかもしれません。