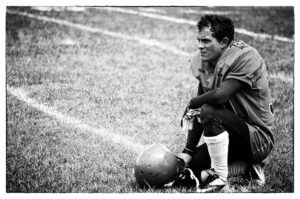私たち一般社団法人日本スポーツメンタルコーチ協会では、これまで数多くのメンタルトレーニング理論や実践方法を学び、研究してきました。その中には「ごきげんでいること」に重きを置いたアプローチも含まれています。感情や気分に左右されず、いつも整った状態でいることを目指すこの考え方は、確かに一部の現場では成果を上げている声を耳にします。
しかし、私たちは長年アスリートや指導者と向き合うなかで、「常にごきげんでいなければならない」という前提が、かえって苦しさを生むケースも目の当たりにしてきました。
禅には「不立文字(ふりゅうもんじ)」という言葉があります。言葉や理論に頼るな、という意味です。理論そのものよりも、それがいま、目の前の人にとってどのように作用するのかを見極める目が必要なのではないか——そのような問いを、私たちは手放すことなく持ち続けています。
今回の記事では、ごきげんメンタルという考え方の光と影を見つめ直し、支援者としての姿勢を再確認する機会としたいと思います。
ごきげんメンタルとは何か
「ごきげんメンタル」という言葉には、直感的なわかりやすさがあります。日々の暮らしやスポーツの現場でも、「なるべく機嫌よくいることが大事だよね」といった共感は得られやすく、多くの人にとって実践的で身近な考え方に映るでしょう。
このアプローチの核にあるのは、「感情に振り回されず、安定した自分でいることが最も高いパフォーマンスを生む」という思想です。たとえば、試合直前に緊張や不安が湧いたとしても、それに飲み込まれることなく、自分の“ごきげん”を保つことができれば、いつも通りの力を発揮できる。これは多くの選手にとって魅力的なメンタルの状態です。
また、「外側の出来事に反応するのではなく、内側からごきげんを選び取る力を養う」というメッセージは、仏教で言う止観の実践、つまり思考や感情を観察し、そこに飲み込まれない態度とも共鳴します。
ごきげんメンタルは、ポジティブ心理学やマインドフルネスの要素も取り入れた総合的なメンタルアプローチであり、多くの現場で役立つ「道具」であることは間違いありません。
しかし、問題はそれが唯一の正解として扱われるときです。「色即是空」という仏教の教えが示すように、どんなに良く見える方法論も、それが絶対化された瞬間に「空(くう)」ではなくなってしまいます。
私たちが感じた違和感の正体
一見前向きに見える「ごきげんでいよう」というメッセージ。しかし私たちは、現場で接する選手や指導者の言動の中に、そこには収まりきらない感情の声を何度も見てきました。
1. ごきげんでいなければならないという自己圧力
「いつも機嫌よくいなければならない」という期待が、自分自身を責める要因になるケースがあります。これは心理学でいう「感情抑圧(emotional suppression)」にあたり、研究によれば長期的にはストレスホルモンの上昇やパフォーマンス低下につながることがわかっています(Gross, 2002)。
また仏教の観点では「煩悩即菩提(ぼんのうそくぼだい)」という言葉があり、煩悩や未熟さもまた成長の糧になると説かれています。ネガティブな感情を排除するのではなく、それを素材として扱う視点が必要です。
2. 感情を整えることが目的化してしまう危険
本来、整えることは手段であるはずです。しかし現場では「整っていない自分はダメだ」という思い込みが起きることがあります。これもまた逆説的に、自己否定を生むトリガーとなるのです。
神経科学の研究では、「感情の自己評価」を繰り返すことで扁桃体が過活動になり、むしろ不安定な状態が長引くことがあるとされています(Etkin et al., 2015)。整えることに執着するほど、心は整いにくくなる──この矛盾に目を向ける必要があります。
3. 「今ここ」へのこだわりが時間軸を奪う
仏教や禅の世界でも「現前(げんぜん)」や「只管打坐(しかんたざ)」など、今に意識を向ける姿勢は重要視されますが、それは決して「過去や未来を忘れよ」という意味ではありません。
むしろ、選手たちは過去の意味づけや未来の希望によって、今を生きる力を得ています。脳科学の視点では、「自己叙述的記憶」や「将来記憶(prospective memory)」が自己アイデンティティの土台になっていることが確認されており(Addis et al., 2007)、今だけに意識を限定しすぎると、自己像が不安定になる可能性すらあります。
ごきげんメンタルが抱える3つの限界
限界① 「ネガティブ感情」の切り捨て
「ネガティブ=悪」という見方は、感情そのものを敵として扱う危険性をはらんでいます。しかし心理学的には、怒りや不安は「環境への適応」や「生存戦略」としての意味を持ちます。
たとえば不安は危険を予測するセンサーであり、怒りは境界線を守る反応です。これを切り捨てることは、「危機感の喪失」や「自己の弱体化」につながります。
仏教でも「喜怒哀楽」はすべて心のはたらきとして受け止められ、そのひとつひとつに意味があるとされます。
限界② 構造的問題を個人の問題にしてしまう
「あなたの機嫌はあなたが決めよう」というメッセージは、ときに暴力的です。
過酷な練習環境、過重なプレッシャー、不適切な指導。こうした環境要因に目を向けず、「ごきげんでいられないあなたが悪い」と責任を個人に帰すことで、構造的な問題が見えなくなってしまうのです。
この点において、ごきげんメンタルが「自己責任論」を強化してしまう危険性は看過できません。
限界③ 「今ここ」に閉じすぎて、人生の文脈が消える
人は「時間を生きる存在」です。心理学では「時間的自己連続性(temporal self-continuity)」という概念があり、過去・現在・未来の自己が一貫していると感じられることが、精神的安定の土台であるとされています。
「今この瞬間だけを生きよう」とするアプローチは、人生の物語性を分断し、自分を見失うリスクすらあるのです。
禅の世界でも「随処作主(ずいしょさしゅ)」という言葉があり、状況に流されず、どこにあっても自分の主人であることが説かれています。それは“今”に縛られるのではなく、今を自在に生きる力を意味します。
それでも私たちが学び続ける理由
ごきげんメンタルという考え方に対して、ここまで様々な限界や違和感を述べてきました。にもかかわらず、私たちはこの理論を完全に否定しようとは思いません。
なぜなら、この考え方の中にも確かな真理のかけらが含まれているからです。
たとえば「状態に意識を向ける」という視点は、支援現場でも有効です。感情や結果に囚われるのではなく、自分の“状態”を観ること。それはまさに禅が重んじる「観照」の姿勢と重なります。
また、「ごきげんを選び取る」という姿勢も、裏返せば主観的に意味づけを選ぶ自由であり、「随所に主となる」という禅語の実践とも解釈できます。
禅では「初心(しょしん)」が尊ばれます。一度学んだことでも、もう一度疑い、もう一度見直す心。私たちがこの理論を手放さず問い続けるのは、それが初心を取り戻すきっかけになるからです。
だからこそ、私たちは学びを止めず、この理論の使い方を問い直し続けたいと思うのです。
理論は使うものであり、信じるものではない
メンタルトレーニングの世界には、さまざまな理論があります。どれも素晴らしい知見を持ち、現場にヒントを与えてくれるものです。しかし、どんな理論であっても、それを信じるものとして扱った瞬間、私たちはその本質を見失ってしまいます。
禅の言葉に「放下著(ほうげじゃく)」というものがあります。すべてを手放してこそ、本質が見えてくる、という教えです。私たちは、理論に執着するのではなく、それを一度手放してみる。そして、本当に必要な時に、もう一度自分の手で使う。そんな柔らかさを持ちたいのです。
支援とは、「正しさを与えること」ではなく、「ともに問い続けること」。理論は、そのための道具にすぎません。
理論に支配されず、理論に依存せず、理論と対等でありながら、それでもなお大切に扱う。
その姿勢こそが、私たちスポーツメンタルコーチが目指す在り方であり、禅の精神にも通じる自由なる心の実践なのです。
最後に 読者への問いかけ
あなたは、どんな理論や言葉に支えられてきたでしょうか。
そして今、それは本当にあなたにフィットしていますか?
それとも、「信じようとしている自分」に無理をしていませんか?
メンタルを整える方法は一つではありません。
むしろ、整っていない自分を許しながら進む道の方が、遠回りに見えて本質に近いこともあるのです。
私たちは、理論を正解として信じ込むのではなく、人生の問いを深めるためのツールとして、これからも使いこなしていきたいと思います。
参考 参照文献一覧
- Gross, J. J. (2002). Emotion regulation: Affective, cognitive, and social consequences. Psychophysiology, 39(3), 281–291. https://doi.org/10.1017/S0048577201393198
- Etkin, A., Büchel, C., & Gross, J. J. (2015). The neural bases of emotion regulation. Nature Reviews Neuroscience, 16(11), 693–700. https://doi.org/10.1038/nrn4044
- Addis, D. R., Wong, A. T., & Schacter, D. L. (2007). Remembering the past and imagining the future: Common and distinct neural substrates during event construction and elaboration. Neuropsychologia, 45(7), 1363–1377. https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2006.10.016
メンタルを整えることで広がる自己表現の幅に音楽を取り入れてみませんか。
「東京のボイトレスクールWACCA MUSIC SCHOOL(https://wacca-music.co.jp/)」
「吉祥寺のボイトレスクールZIGZAG MUSIC SCHOOL(https://zigzag-music.jp/)」
「立川のボイトレスクールDECO MUSIC SCHOOL(hhttps://deco-music.jp/)」
「大宮(埼玉)のボイトレスクールNOPPO MUSIC SCHOOL(https://noppo-music.co.jp/)」
での受講を検討してみてはいかがでしょうか。オンラインレッスンにも対応しています。